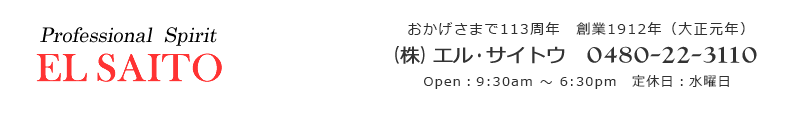香港からこんにちは![]()

アヘン戦争終結後の南京条約により、香港島が英国に割譲され、1842年に始まった英国の植民地統治。
150年以上に及ぶ自由放任、自由競争主義を核とした英国流の統治は、香港に目覚ましい発展をもたらしました。
水深など貿易港に最適な天然の良港、どこへ行くにも近い東アジアの中心という立地的な優位性、明朗快活で闊達、頭の回転が早い華南地区広東省の香港人資質。。。

あの英国が、それらを全く知らずにアヘン戦争で偶然香港を手に入れたわけがありません。 英国にしてみれば、香港は早くから狙った獲物だったはず。
現に、宗主国イギリス政府より任命された香港総督は歴代、英国君主の名代として大きな権限を持ち、政治的にも軍事的にも大変重要視されたポストだったといいます。
そして香港が持つあらゆる可能性と好諸条件を見抜いていた英国は、それらを一体化させながら、自由放任主義と英国流の統治で、香港をアジア一の金融・貿易の中心地に作りあげていきました。

とはいえ、宗主国イギリスに対し従属国香港、という力関係であることには違いない、それが植民地統治であり、植民地経済。
英国人と香港人の利益が衝突するような場面では、香港側の意見は巧妙にあっさりと無視され、宗主国、支配層に利益がもたらされさえすればそれでよいという、英系資本の経済独占支配は続きました。
発券業務を含む金融、不動産、通信、電力、ガス、交通機関、教育、医療、道路や橋、トンネルなどのインフラや、各種公益事業においての権益など、香港経済は全英系資本により占められました。 この名残や影響は、現在の香港社会でも、あらゆる場面で見られます。

日清戦争、2度の世界大戦、「暗黒の3年8ヶ月」と呼ばれる日本占領時代、朝鮮戦争、文化大革命、オイルショックなど、国際情勢の混乱に影響を受けた経済危機の波を幾度も乗り越え、その都度目覚ましい発展を遂げてきた香港。
その経済を根幹で支配していたのは英系資本でしたが、支えていたのは他でもない、地元香港人。
もともと香港には、小さいながら当地資本といえるものが、実はあるにはありました。
主に中国内地との交易や小中規模の食品加工業、プラスティックなどの軽工業、玩具から薬品まで製造業や小売り業、バス会社などがそれで、後に財閥化する華人資本のいくつかは、ここからスタートしているものもあります。
また、古くからある華人一族による、例えば、利 (Lee)家 (Opium King と呼ばれた利希慎 (Lee Hysan) が、アヘン商人と組んだオピウム (アヘン) の取引きで巨額の財を成した父親からビジネスを受け継ぎ、のちに不動産や土地開発にも着手した、香港の名門華人ファミリー) の資本などもありました。

本当の意味で、華人資本が香港植民地経済構造の隙間へ入り込み、資本の力関係の変化が如実に見え始めたのが、1970年代。 戦後香港で勃興、1960〜70年代の不動産ブームで急成長した新興財閥が、英系資本を脅かすような形で発展、コングマリットとして巨大化していきました。
鴻基地產發展有限公司 (Sun Hung KaI Properties Limited)、新世界發展 (New World Development)、恒基兆業地產 (Henderson Land Development Company Limited)、そして、長江實業集團有限公司 (Cheung Kong Holdings Limited)。
これら香港の4大財閥の事業は、不動産開発・投資、プロパティマネジメント、ホテル経営、証券投資、施設管理、インフラストラクチャー、通信、などに多岐に渡るもの。

それまでは、英系資本が植民地政府である香港政庁との強い関係を背景に、香港経済を独占支配していましたが、不動産進出を契機に勢いを増した華人資本が支配層に加わり、最終的には英系資本を華人資本が買収すると言う、力関係の逆転現象が起こっていきました。
香港の優れた投資環境に引き寄せられた金融、不動産、商業などのサービス分野が世界中から進出し、多国籍企業がアジア地域の統括本部を香港に置くなど、華人資本の台頭が、対中ビジネスだけでなく、結果的には世界中の多様な資本をますます香港に引き寄せるという流れになっていったのです。

次回は、ある華人財閥総裁の人生から見える、返還直前までの香港の軌跡をたどってみたいと思います![]()
JUN